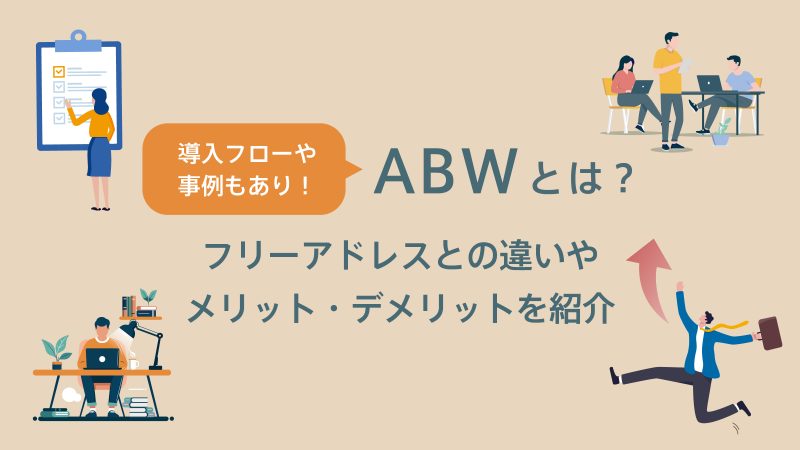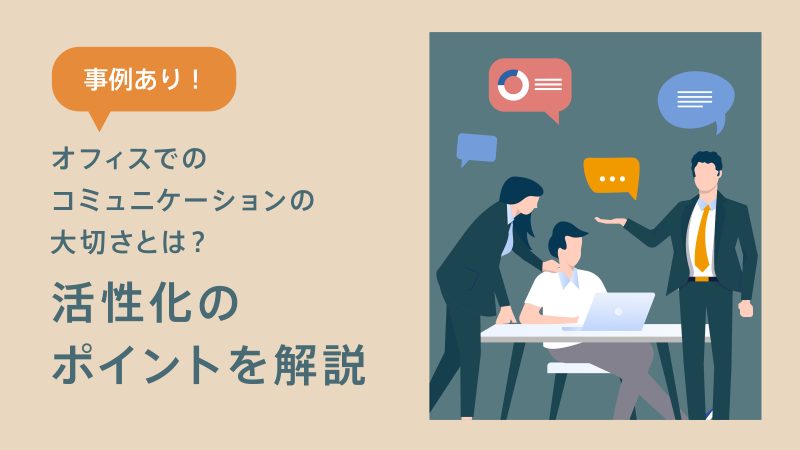ハイブリッドワークとは?導入企業事例や課題、成功させるポイントを解説
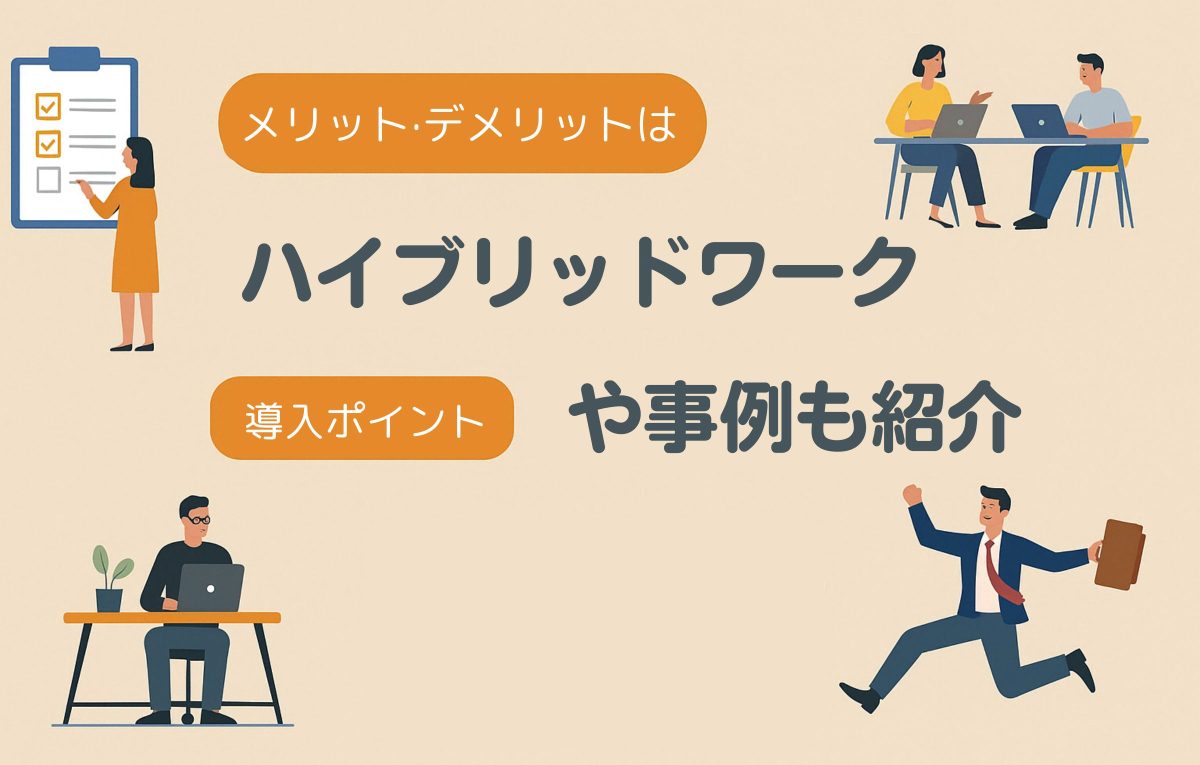
近年は、テレワークが普及し、オフィスワークの重要性が見直されています。そうした中、オフィスワークとテレワークを組み合わせた柔軟な働き方である「ハイブリッドワーク」がテレワークの弱点を補い、オフィスの強みを発揮できるワークスタイルとして必要性が高まっています。
ハイブリッドワークには、具体的にどのようなメリット・デメリットがあり、導入を成功させるにはどのようなポイントを押さえる必要があるのでしょうか。
本記事では、ハイブリッドワークの意味や必要とされている理由、導入のメリット・デメリットについて解説します。ハイブリッドワークを導入している企業もご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
オフィス事例集など、オフィス構築に役立つ資料のダウンロードはこちら
目次
1.ハイブリッドワークとは、オフィス勤務とテレワークを組み合わせた新しい働き方
近年、働き方も時間の使い方も大きく変化し、テレワークが普及してからは、働く場所もオフィスだけでなく自宅やカフェ、コワーキングスペースなど選択肢が広がりました。
そんな中、最近よく耳にするのが「ハイブリッドワーク」という働き方です。
ハイブリッドワークとは一体どのような働き方なのでしょうか。 こちらの章で解説していきます。
1-1. ハイブリッドワークは英語で「Hybrid work」
ハイブリッドワークは英語表記だと「Hybrid work」と書きます。
「ハイブリット」と「ハイブリッド」のどちらが正しいのかと悩まれる方もいるかもしれませんが、”組み合わせる”という意味を持つ「Hybrid」の英語表記の末尾は「t」ではなく「d」であることから、正しい読み方は「ハイブリッド」であると考えられます。
1-2. ハイブリッドワークとは、オフィスワークとテレワークを組み合わせた働き方のこと
ハイブリッドワークとは、オフィスワークとテレワークなど、異なるワークスタイルを組み合わせた柔軟な働き方のことです。近年は、テクノロジーの進展や「働き方改革」の推進によってテレワークが普及しましたが、オフィスワークの価値を見直す動きも強く、そうした中でハイブリッドワークが注目されています。
ハイブリッドワークの特徴は、オフィスワークとテレワークを組み合わせ、業務内容やライフスタイルに応じて、柔軟に選択できることです。これにより、チームワークを重視する業務はオフィスでおこない、個人で集中する業務は自宅やサテライトオフィスでといった、目的に応じた働き方ができます。
国土交通省の「令和5年度 テレワーク人口実態調査」では、コロナ禍を経てハイブリッドワークを実施する割合が増加傾向にあるという結果が出ました。今後も、この動きは強まっていくと考えられます。
参考:国土交通省「令和5年度 テレワーク人口実態調査-調査結果-」(2024年3月)
2. ハイブリッドワークとテレワークの違いは出社の有無
ハイブリッドワークとテレワークの違いは、勤務場所の柔軟性と出社の有無です。
ハイブリッドワークはオフィスワークとテレワークを組み合わせた働き方であり、従業員は必要に応じて出社します。
しかし、テレワークは出社をせず、自宅などで勤務する働き方です。そのため、従業員同士や取引先などとのコミュニケーションは、基本的にオンラインのみになります。
ハイブリッドワークとテレワークにはそれぞれメリットがありますが、業務効率の向上、企業文化の醸成などにおいては、オフィス勤務の時間があるハイブリッドワークのほうが効果的だといえるでしょう。
オフィス事例集など、オフィス構築に役立つ資料のダウンロードはこちら
3.ハイブリッドワークが必要とされている理由
ハイブリッドワークは、どのような理由から企業で導入されているのでしょうか。ハイブリッドワークが必要とされている理由について解説します。
3-1. テレワークの弱点を補うため
ハイブリッドワークは、テレワークの弱点を補うために多くの企業で導入されています。テレワークには時間や場所の自由度が高いというメリットがある一方で、いくつかの課題も存在します。
自宅のみで仕事をすることによるコミュニケーションの減少やセキュリティ・健康面の不安は、テレワークのデメリットです。テレワークのこうした弱点は、必要に応じて出社するハイブリッドワークによって、ある程度補うことができます。
ハイブリッドワークによって出社の機会が増えれば、コミュニケーションの時間を適切に設けることができ、部下の業務管理もしやすくなります。テレワークの弱点を適切に補い、業務効率化や組織運営の円滑化に寄与するでしょう。
3-2. オフィスの強みを活かし、組織の生産性を高めるため
オフィスワークの最大の強みは、リアルな対面コミュニケーションです。オフィスの強みを活かし、組織の生産性を高められることも、ハイブリッドワークが求められている大きな理由です。オフィスワークには、アイディアを出し合う、上司や同僚が間近にいるためいつでも質問・相談ができるといった、オフィスならではのメリットが数多くあります。
このようなオフィスの強みは、従業員一人ひとりの生産性だけでなく、組織としての生産性向上にも大きく貢献するでしょう。
オフィス事例集など、オフィス構築に役立つ資料をご提供しています。
4.ハイブリッドワークのメリット
ハイブリッドワークのメリットは、主に下記の5つです。詳しく見ていきましょう。
4-1. 生産性の向上が期待できる
オフィス・自宅・サテライトオフィスなど、従業員がもっとも生産的であると感じ集中できる環境をみずから選べるため、より効率的かつ生産性の高い業務進行を実現できます。気分や当日の業務内容によって働く場所を選べるのは、従業員にとっても大きな魅力です。
4-2. 従業員のモチベーションアップ
テレワークとオフィス勤務の選択肢があることで、子育てや介護など個々人の状況に合わせたワークライフバランスのとれた働き方ができることは従業員の働きやすさにつながります。この自由度の高さは従業員のワークライフバランスを大幅に改善し、仕事に対するモチベーションと満足度の向上に直結します。
また、個々のスケジュール管理なども自発的におこなうようになり、従業員の自立性向上も期待できるほか、社員満足度向上による定着率アップにも貢献できるでしょう。
4-3. オフィスの省スペース化によるコスト削減
ハイブリッドワークを取り入れることでこれまでのようにすべての従業員が同時にオフィスに出社する必要がないため、必要なスペースを最適化することが可能です。
また、オフィスの省スペース化はテナント費用をはじめ、水道光熱費、設備費用など多くのランニングコストを削減することができます。
4-4. 人材確保がしやすくなる
ハイブリッドワークを導入することで、勤務地や採用活動地など地理的な制約が軽減され、企業は全国規模で、各地の優秀な人材確保がしやすくなります。
また、柔軟な働き方や居住地に依存せずに仕事ができる就業環境を求める求職者に対しての差別化にも効果的で、これにより企業は人材の多様性を尊重し、優秀な個人を迎え入れやすくなりました。
4-5. コミュニケーション不足を解消できる
ハイブリッドワークを導入すると、従業員同士のコミュニケーション不足を解消できます。テレワークのみだと、コミュニケーションはどうしても不足しがちですが、適度に出社することで、他部署の従業員とも交流の機会をつくれるでしょう。
また、業務のわからないところを上司や先輩に相談したい、ざっくばらんな対話を通じてアイディアを得たいといった場合、出社すれば難なく目的を達成できます。
コミュニケーション不足による問題が解消しやすくなることは、ハイブリッドワークの大きなメリットです。
5.ハイブリッドワークの課題とデメリット
ハイブリッドワークには多くのメリットがありますが、解消すべき課題・デメリットもいくつかあります。主な課題とデメリットは下記の5つです。
5-1. 社内コミュニケーションの減少
テレワークと出社勤務のうち、テレワークの頻度が高くなると社内コミュニケーションの減少が懸念されます。気軽な相談・報告などもチャットや画面越しの交流が主体となってしまい、社内コミュニケーションの不足からストレスの原因になる可能性もあります。組織としての一体感が薄れてしまい、孤独感を抱くことにもつながりかねません。
5-2. 業務効率の低下
在宅などのテレワーク環境下では集中力の継続が難しく、業務効率の低下に繋がる恐れがあります。また、ハイブリッドワークを導入している企業では、一方はオフィスワーク、もう一方はテレワークなどと打ち合わせをするだけでも異なる働き方をしている従業員が多く見られます。
ストレスなく業務を遂行できる通信環境のオフィスに比べると、テレワークは通信環境によって電波が悪い場合があり、打ち合わせをしていてスムーズにやりとりができないなどビデオ通話によるコミュニケーションの質には限界があります。さらに、対面で常に仕事ができるオフィスワークに比べて、ハイブリッドワークはプロジェクト進行やタスク管理が困難になってしまう場合もあります。
5-3. 勤怠管理・評価の困難性
ハイブリッドワーク環境下では、常に同じ空間で業務をおこなわないため、勤怠や評価の管理が難しくなります。プライベートと業務の境界線が曖昧となり、労働過多になってしまうリスクが出るだけでなく、動きが見えやすい出社する人としない人に評価の差が生まれてしまうなど、公平性の面でも課題も上げられます。
5-4. 情報セキュリティの脆弱性
従業員が異なる場所でフレキシブルに業務を遂行することは多くの利点がありますが、同時に情報セキュリティにおける懸念事項も浮上します。従業員が自宅やカフェなどの公共の場で業務をおこなう場合、通信経路や端末のセキュリティの確保が難しくなります。Wi-Fiの利用や外部からのアクセス機会が増加することで、機密情報が不正アクセスや盗聴のリスクにさらされる可能性が高まります。
また、ハイブリッドワークではテレワークを織り交ぜることで社内データを外部に持ち出すことになるため、顧客情報や機密情報などの情報が外部に流出する危険性が高まることも大きな課題の一つです。貸与PCやスマートフォンの盗難・紛失などのリスクも潜んでいます。
5-5.従業員間で情報格差が生まれる
従業員間で情報格差が生まれることも、ハイブリッドワークのデメリットです。適度にオフィスワークをおこなっている従業員とテレワークが中心の従業員では、コミュニケーションの頻度や質に差が生まれます。居住地や家庭の事情などによりテレワークが中心の従業員は疎外感を抱きやすく、モチベーションの低下につながることも考えられます。
また、前述のとおり、ハイブリッドワークを導入すると、オフィスワークとテレワークの従業員が混在することになるため、オフィスワークのみの場合に比べ、情報共有や意思疎通が滞る可能性があります。そのようなことにならないよう、適切なコミュニケーションの仕組みやルールづくりが必要です。
オフィス事例集など、オフィス構築に役立つ資料をご提供しています。
オフィス構築 資料一括ダウンロード
6.ハイブリッドワークを成功させるためのポイント
ハイブリッドワークを成功させるには、いくつかのポイントを押さえる必要があります。主なポイントは下記のとおりです
6-1. ハイブリッドワーク運用のルール作り
ハイブリッドワークを導入する前に、運用に伴うルールを明確に定めておく必要があります。従業員によって出社日が異なるため、出社人数がオフィスのデスクのキャパシティーを超えないように調整するなどハイブリッドワークならではの調整が必要になります。出勤日数や時間・曜日など、各従業員にある程度の裁量を持たせたうえで策定すれば、柔軟な環境を構築することができます。
また、始業時間や終業時間・休憩時間などの勤怠管理はもちろん、通勤手当の支給をどうするかなど細かな規定なども検討しておくようにしましょう。
さらに、オフィスワークとテレワークの従業員で評価などに不公平が生まれないようにする配慮も必要です。
6-2. ICTを活用した環境づくり
スムーズなハイブリッドワーク導入にはICTを中心としたシステム整備が不可欠です。
近年ではテレワークやハイブリッドワーク構築のためのICTツールも数多く登場しているため、積極的に活用することをおすすめします。
<ハイブリッドワークの導入に役立つツール>
・コミュニケーションツール
・ウェブ会議システム
・勤怠管理システム
・クラウドPBX(インターネットで電話を利用できるサービス)
6-3. ハイブリッドワークに適したオフィスデザイン
出社とテレワークを自由に選択できる環境において、従業員が出社したくなるオフィス構築も非常に重要です。
ABWやフリーアドレス制など柔軟かつ効率的な働き方ができる環境はもちろん、おしゃれなレイアウトやインテリアなど、トレンドを意識したオフィスデザインを意識するようにしましょう。設備・デザイン・雰囲気など多角的な側面から空間を構築し、変革を続ける働き方をサポートできるオフィスをつくることで、従業員のウェルビーイングや定着率向上につながっていくでしょう。
従業員のモチベーションアップをはじめ、ブランディングや採用にも効果的なオフィスデザインについては過去コラム【オフィスデザインのトレンドをご紹介!採用や企業イメージアップにも効果的】でご紹介しているので、興味がある方はぜひご覧ください。
オフィス事例集など、オフィス構築に役立つ資料のダウンロードはこちら
7.ハイブリッドワーク導入企業
ハイブリッドワークは、すでに多くの企業で導入されています。ここでは、ハイブリッドワークを導入した企業の取り組みをご紹介します。
7-1. 日本全国でハイブリッドワークをおこなっている企業の割合は約3割
内閣府の調査によれば、完全なテレワークを除いたハイブリッドワーク導入率は2023年3月時点で全国で25.5%、都心部に限定すれば42.2%。
業種や職種による差はありますが、概ね全体の3割程度の企業がハイブリッドワークを導入していると言えます。コロナ禍以前が全国7.5%、都心部14.3%だったことを踏まえると、ハイブリッドワークを導入した企業は3~4倍に増加している状況です。
参考:内閣府(第6回 新型コロナウイルス感染症の影響下における生活意識・行動の変化に関する調査)
7-2. ハイブリッドワークを導入している企業の事例
実際にハイブリッドワークを導入している企業事例についてご紹介いたします。
7-2-1. GOOD PLACE(旧コスモスモア)
コロナ禍以前からハイブリッドワークを導入しているGOOD PLACE(旧コスモスモア)。
働く場をつくるオフィス事業や総務アウトソーシング事業、リノベーションをはじめとする建築事業を展開する弊社は、コロナ禍に先んじてテレワークを導入しており、現在も引き続き個人の裁量で行うことができます。以前はリモートワークは週4回まで、事前申請が必要という規定がありましたが、現在では個人の裁量に委ね、プロジェクトや業務の内容に応じて、リモートと出社をハイブリッドで運用しています。
参考:GOOD PLACE採用サイト「福利厚生」
ミライのお仕事「有給休暇取得で手当支給!株式会社GOOD PLACEの多様な働き方を促進させる数々の施策とは」
7-2-2. Google:週3日の出勤を勤務評価に追加
完全テレワークを導入していたGoogleは、2023年6月にハイブリッドワークポリシーを更新。週3日の出勤を勤務評価の一部に加えることとなり、常にオフィスに出社しない従業員にはリマインドが送信されるようになったそうです。
Googleの最高人事責任者であるフィオナ・チッコーニ氏は、オフィス勤務について 「直接集まることに代わるものはない。同じ部屋で一緒に仕事をすることが前向きな変化を生むことには疑いの余地はない。」 と述べています。
7-2-3. 東芝:週3日の出勤を勤務評価に追加
原則出社を掲げていた東芝は方向性を見直し、事務や研究開発など在宅勤務可能な職に就いている従業員に対して、国内なら全国どこでも居住してもいいとする新制度の導入を2022年に発表しました。「業務内容が全て在宅勤務で対応でき、生産性を維持・向上できるのであれば理由は問わない。 」とのことです。明確な出社日数などは定められていませんが、従業員の判断により業務内容に応じて在宅・出社を自由に選択できるハイブリッドワークを採用しています。
参考:東芝、原則出社を撤廃へ 4万4000人対象にコロナ後も(日本経済新聞 電子版、2022年7月13日)
7-2-4. サイボウズ:働き方の希望を社員がみずから宣言
コロナ禍以前から先駆けてハイブリッドワークを導入していたサイボウズ。
2010年の時点で在宅勤務のテスト運用を始めており、2018年4月からは100人100通りの働き方ができるようになっています。「午前中は常に在宅勤務をします」「水曜日は在宅勤務をします」といった希望の働き方を社員に宣言してもらい、突発的な場合は申告の上で上長から承認されれば認められるそうです。
参考:サイボウズ(サイボウズの「テレワーク」に関する情報を公開します)
8.ハイブリッドワークを効果的に導入し、企業の成長に役立てよう
ハイブリッドワークとは、オフィスワークとテレワークを組み合わせた働き方のことです。ハイブリッドワークを導入すると、生産性の向上をはじめとしたさまざまなメリットがあります。
一方、従業員同士のオフィスワークとテレワークのタイミングがずれることにより、コミュニケーションの不備や情報格差といったデメリットも生まれるため、導入する際にはそれらを踏まえた運用ルールづくりが必要です。ハイブリッドワークを効果的に導入し、企業の成長に役立ててください。
オフィス事例集など、オフィス構築に役立つ資料のダウンロードはこちら
- ハイブリッドワークで懸念される課題である「コミュニケーション不足」を解消するには?
- ①出社したくなる「マグネットスペース」(カフェやリフレッシュエリア)をオフィスに設置し偶発的な交流を促すこと
②全員出社日を設けるなど意図的な対面機会を仕組み化すること
③オンライン・オフラインの会議室設備を強化し、情報共有と発言の公平性を保つこと
これらの施策がおすすめです。 - ハイブリッドワークに適したオフィスデザインとは、具体的にどのようなものでしょうか?
- ハイブリッドワークに適したオフィスは、活動に応じた場所の選択肢を提供するデザインです。
コラボレーションエリア: 偶発的な交流を生むカフェスペース、カジュアルなミーティングエリアなど。
集中エリア: ノイズを遮断できるフォンブースや個室、図書館のようなサイレントエリアなど。
ITインフラの強化: どの場所でも安定して接続できる高速Wi-Fi、Web会議に必要な高性能カメラやマイクを備えた会議室(ハイブリッド会議室)の設置など。
これにより、従業員は出社した際に自宅ではできない業務(対面での密な連携や集中作業)を効率的に行えるようになります。 - フリーアドレスやABWを導入する際の最大の注意点は何ですか?
- 最大の注意点は導入後の定着です。席を探す時間が増えたり、部署間の連携が希薄になったりするリスクがあります。
対策: ①ITインフラ(Wi-Fi、クラウドPBXなど)の完備、②座席予約システムの導入、③部署ごとの集まりやすいコミュニケーションエリアの設置など、運用ルールと環境整備が不可欠です。